トピックス
[学生インタビュー]国際学部国際社会学科4年小向加奈さん(「第15回日台 文化交流青少年スカラシップ」(日本工業新聞社・産經新聞社主催)大 賞受賞者)
本学国際学部国際社会学科4年の小向加奈さんが、「第15回日台文化交流青少年スカラシップ」(日本工業新聞社・産經新聞社主催)において、見事大賞を受賞しました。これは若者による日本と台湾の文化交流を促進するため実施されているもので、小向さんは「スピーチ部門」で台湾の伝統芸能について中国語でスピーチし、見事大賞に輝きました。
小向さんに今回の大賞受賞についていろいろお話をお聞きしました。

―「日台文化交流青少年スカラシップ」大賞受賞、おめでとうございます。大賞ということで、大変栄誉あることだと思いますが、今回はどのような内容をスピーチされたのですか?
私は大学2年の時に台湾に1年留学をしました。その時に台湾人の友だちと一緒に台湾の代表的な伝統人形劇「布袋戯」を鑑賞しました。そこで、台湾では非常に伝統芸能が市民の間に浸透していると感じました。そのことから、日本と台湾の伝統芸能の「保存」についてどのように違うのかということについて関心を持ち、大学でも研究を続けてきました。今回のスピーチでは、そのことをベースにして日台間の「保存」という考え方の違いについてお話ししました。

―具体的にはどのような点が異なるのでしょうか?
日本では、「重要無形文化財」など、公的機関で文化財を登録・認証してもらい保護につなげていくといった考え方がありますが、台湾ではそれをさらに進め、登録のみでなく実質的に市民の間に根付かせ、身近にしていくという活動が盛んです。昔使われていた行政機関の建物を改修して伝統芸能を広めていく舞台にするという手法も多数展開されていて、土地や建物と伝統芸能、文化を結び付けていくというところがとても面白いです。
―こういった部分で、伝統文化の保存について台湾に学ぶところが多いと考えたわけですね。
はい。このテーマを含め、日台間の文化の違いや、台湾の歴史などについてこれからも学び続けていきたいと思っています。
―今回のスカラシップに応募したきっかけは何ですか?
大学で所属しているゼミの松金公正先生から勧められたことが直接のきっかけです。ゼミには学部3年生から博士課程の学生まで在籍しており、様々な考え方の学生とディスカッションすることでいろんな視点から物事を見ることができ、価値観の幅も大きく広がったと思います。
―中国語でのスピーチだったそうですが、語学力を養成する上で何か気をつけたことはありますか?
やはり基礎をしっかり、1~2年生の授業をおろそかにしないといった部分がベースになると思います。あと、留学先があまり日本の学生がいない環境で、台湾の学生とのコミュニケーションを深める環境としては最高でした。

―それでは最後に、この3月で卒業ですが、後輩の皆さんに何かメッセージがあればお願いいたします。
大学生活は長いようで本当にあっという間です。イベントやサークル活動など、何でも積極的に参加したほうがいいです。経験して分かることも多いですし、大学内でもいろんな人が様々な活動をしていますから、どんどん参加していってほしいですね。 あと、自分の強みを持つことも大切だと思います。国際学部では様々なことが勉強できますが、せっかく入学した国際学部、関心を持った国を徹底的に掘り下げてみるとか、語学を納得いくまでやってみるとか、興味があることをとことん勉強することがやっぱり大事かなと思います。
―ありがとうございました。小向さんには日台の架け橋としての今後の活動も期待しています!
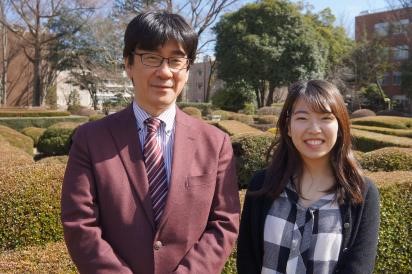

~~松金先生よりひとこと~~
おめでとうございます。小向さんは本当に成長したなと改めて実感しています。ほんの1年ぐらい前までは、ゼミでの態度を見ていても何をしたらいいのか、どの方向に向かっていけばいいのかよくわからない感じでいたと思いますが、4年生での台湾への短期留学(海外臨地演習)と卒業論文を通して、日本と台湾の交流に何が必要なのか、具体的に相手を説得させるだけのものを得られたことが今回のスピーチにも反映された。それが大賞受賞につながったのだと思っています。
(取材日:平成30年3月6日 本学峰キャンパスUUプラザにて)
