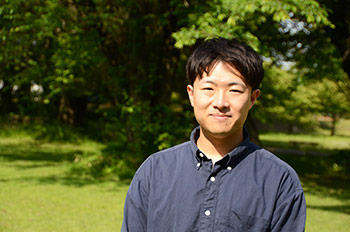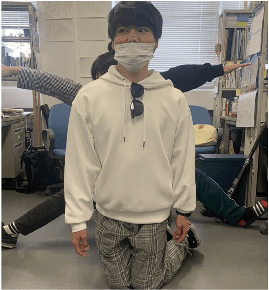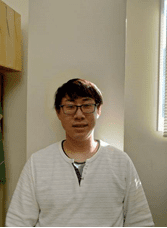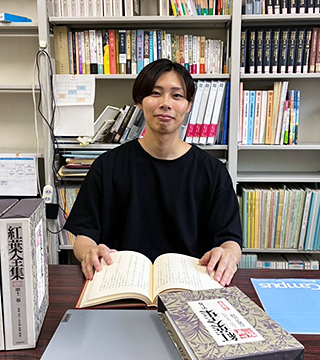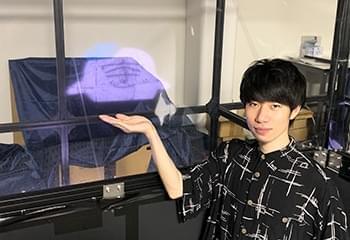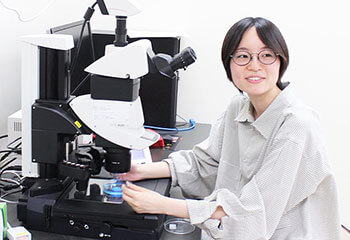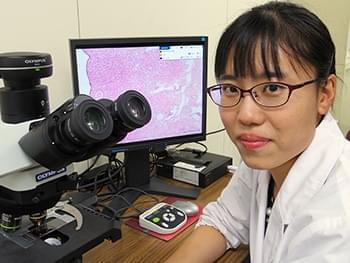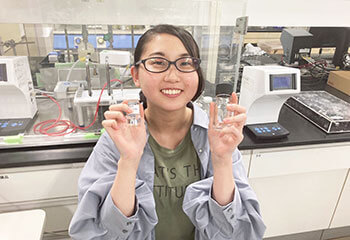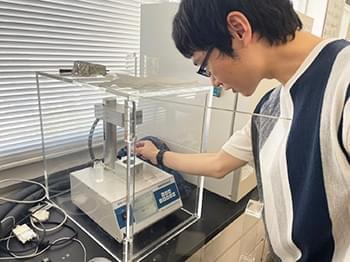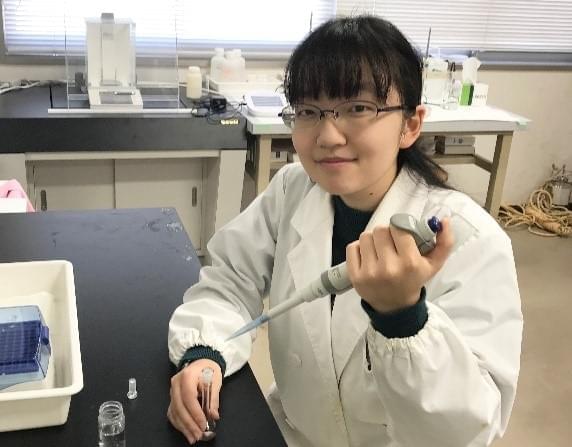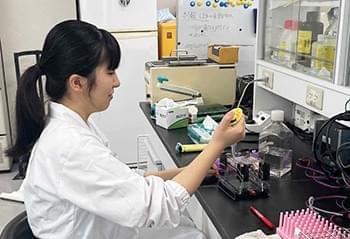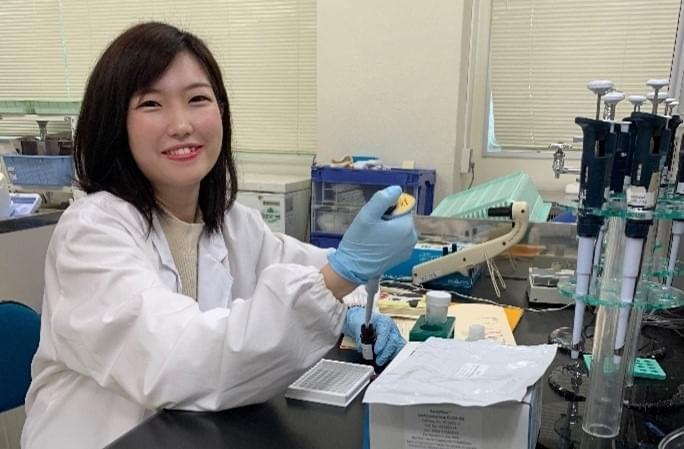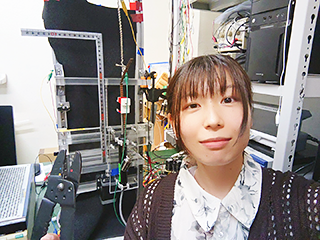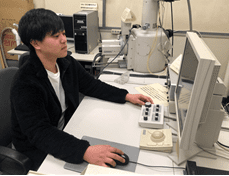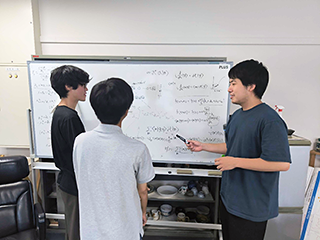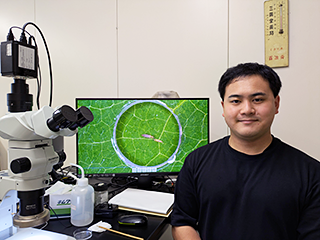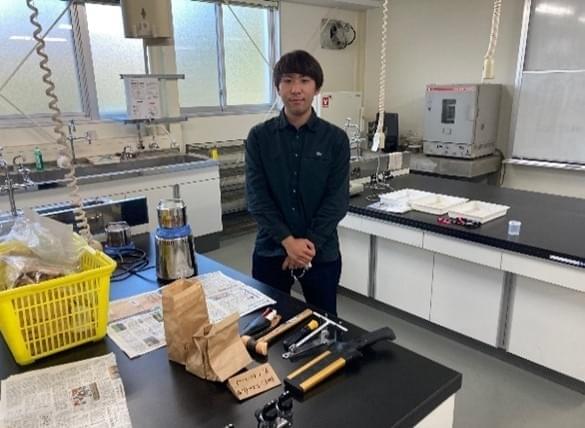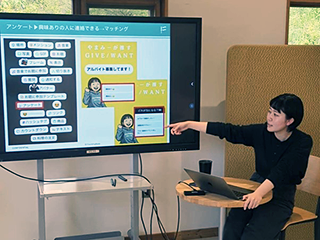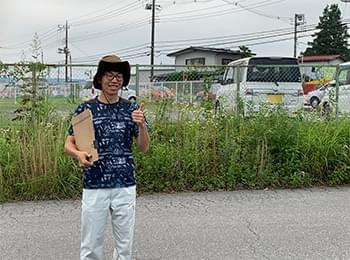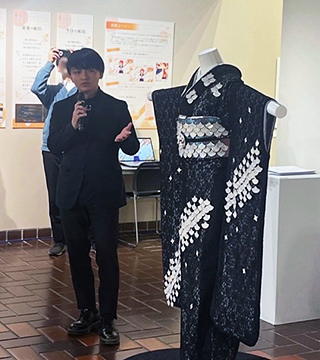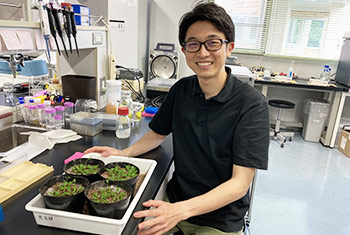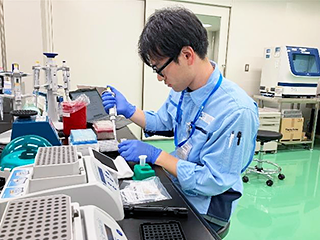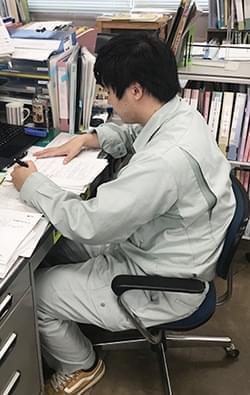- 山本 あゆみ
-
2024年度修了生
株式会社FoundingBase
自分の好奇心に従って、未来を描き続けた2年間
私は学部時代に、幅広い定義を持つ「まちづくり」についてもっと学びたいと思い、以前から関心のあった「高校生のための地域の居場所」について研究するために大学院へ進学しました。大学の授業やゼミでは、これまで関わることのなかった多様な年代・国籍の方々と時間を共にする中で、自分の「当たり前」や「価値観」が次々と覆されていきました。
また、福島・栃木・京都など、高校生の居場所づくりを先駆的に実践している現場にも自ら飛び込み、学びを深めてきました。
この2年間で私が最も大切だと感じたのは、「対話をすること」です。目の前の人を知ること、そして自分を知ってもらうことの大切さを実感しました。
人とまちと協働し、創造していくことには明確な答えがなく、常に探究の連続です。現在は北海道の小さな町で、コミュニティデザインの実践に取り組んでいます。大学での経験の延長線上にあるこの日々の中で、答えのない未来に向かって探究を続けられていることがとても幸せです。
- LIANG XIN
-
2023年度修了生
宇都宮大学大学院地域創生科学研究科博士後期課程
学ぶことの楽しさを味わい、視野を広げることの喜びを知った
私は、博士前期課程を修了後、健康促進について、より深く研究したいと考え、博士後期課程に進学し、現在は、健康行動促進に関する研究を行っています。
博士前期課程の2年間、さまざまな分野で研究を行っている学生同士と交流しながら、各自の研究内容に対して意見交換して研究を進めてきました。また、多様な分野の科目を学ぶことで、研究に役に立つスキルを身につけることができ、新たな視点に気付くことができ、学びの楽しさを体感しました。学会に参加して研究成果を発表し、多くの研究者と討論することも大変貴重な経験でした。
また、ベトナムやアフリカから来校した学生とのワークショップに参加することで、海外の学生との交流を通じて、学術的な知識だけでなく、視野が広がり、人生を豊かにできると実感しています。大学院での経験は、私にとって貴重なものとなりました。今後も大学院での学びを活かしながら、研究を進めていきたいと思います。
- 王 立婧(オウ リジン)
-
2021年度修了生
Baidu(バイドゥ)
自分で考える、世界が変わる
私は学部の時から、「子どものココロ」「子育て」に興味を持ち、より専門的な知識を得るために、大学院へ進学し勉強することにしました。「本にかかれている知識を学ぶ」、それだけではなく、私は主指導先生のご指導のもとに、子育ての現場に行きました。そこで、様々な人々と関わりながら、協力し合い、私は自分の研究の意義をより深く考えることができるようになりました。
そして、何よりも大切なのは、私は「自分で考える」というスキルを身につけました。私の研究は「子どもの主体性を大切にする関わり」であって、そこで分かったのは、子どもにとって自分で考え、自分で行動することは自信を持つことに大きく繋がるということです。大人でも同じです。行動して小さな成功体験を蓄積することで、成功するサイクルが生まれてくるのです。今の自分が、中国検索エンジンの最大手であるBaidu(バイドゥ)で働けるのも、私は「自分で考える」力の大切さを理解できたおかげだと思います!
農業・農村経済学プログラム
- RAKOTONDRASOA Voloina Stelly
-
2024年度修了生
Ministry of Agriculture and Livestock In Madagascar
Utsunomiya University: Enhancing My Expertise for Sustainable Agriculture in Madagascar
My name is RAKOTONDRASOA Voloina Stelly, and I'm from Madagascar. My journey to becoming an alumna of the Master's program in Agricultural and Rural Economics at Utsunomiya University in Japan was transformative. As an agricultural extension worker for over a decade, specializing in rice cultivation with the PAPRIZ project in the Analamanga Region of Madagascar, I sought to deepen my understanding and refine my strategies.
Utsunomiya University provided the ideal environment. I am especially thankful for the unwavering support of all the professors, particularly Professor KATO Koji, my supervisor, Ayane Kikuchi San, my tutor, and all students within my laboratory. Their expertise and collaborative spirit greatly assisted my research endeavors. The university's commitment to international collaboration and its supportive environment for students from diverse backgrounds truly enriched my learning. The program's focus on holistic understanding through case studies allowed me to deepen my knowledge of agricultural economics and refine my extension strategies. These included participating in an international conference and visiting regions undergoing revitalization efforts, which deepened my understanding of community development.
I was honored to receive a JICA scholarship that enabled this enriching experience. The comprehensive knowledge I gained at Utsunomiya University is invaluable as I return to Madagascar, ready to contribute to a more sustainable and food-secure future.
視点を変えて、視野を広げていこう
学部生時代は、工業系大学で経営を専攻していました。地域への思いを抱いて大学院に入学しましたが、農業分野のことについては、当時の私はまったくの素人でした。授業が進むとともに、農村地域とその経済的・社会的構造に対し、理解を一層深めることになりました。特に、修士論文で扱うのは「農業は立国の根本」とする中国の、都市近郊農村であり、「これまでの知識では足りない」、もしくは、「一部は適用範囲外だ」と考えなくてはなりません。自分の持っている知識の限界を明らかにし、そしてもう一度それを広げることは、常に大事にしました。
その目標を達成するのに、先生方や、研究室の仲間たちとのコミュニケーションが助けになりました。ディスカッションによって、「なぜこう考えるのか」「なぜこうしたのか」など、根本的な問題を問い直すことができました。様々な分野を専攻する人と共に学ぶことを通し、異なる視点を見つけることもありました。また、実際に地域に足を運んで、住民と話し合ったり、現場の様子を見たりすることは、教科書にある事実の検証であり、新しい知見の獲得につながりました。これらの活動から得た貴重な経験は、仕事にも今後の人生にも活かしていきたいと思います。
建築学プログラム
- 竹澤 くるみ
-
2022年度修了生
宇都宮大学大学院地域創生科学研究科博士後期課程
想像しなかった可能性に気づく、チャレンジできる環境
私は博士前期課程を修了後、博士後期課程に進学しました。都市の視点から社会課題を捉え、解決方法を提案することで、公正な社会の実現に貢献できる「研究者」を目指して日々研究をしています。現在は、「超高齢社会に対応した医療・介護計画のあり方」に関して研究しています。
大学院では、国内学会だけでなく、ベルギー,フィリピンでの国際学会で口頭発表も経験しました。また、研究室の同期や後輩の研究にも関わったり、学外のプロジェクトやコンペなどに参加したりと、自分の研究以外の活動にも積極的に取り組んできました。その結果、課題発見力や多角的視点で見る力、コミュニケーション能力等を伸ばすことができました。様々な学びの機会に全力で取り組んだ結果、学部入学当初は考えもしなかった「博士後期課程進学」「研究職」という選択肢に気付き、目指す方向を明確にすることができました。
大学・大学院は、自分の可能性を広げられる場所です。
皆さんも何かに全力で取り組んでみたら、想像しなかった道が開けるかもしれません。
- 大場 稜平
-
2021年度修了生
三井住友建設株式会社 建築本部 構造設計部
研究を通して鍛えるべきこと
私は現在、建築物の構造設計の仕事に携わっています。大学院時代の研究から得られた専門知識が仕事に直結することもありますが、それはごく僅かであり、社会人も日々勉強です。建築物はその立地条件・デザイン・構造種別などによって多種多様であるため、設計業務は常に明確な答えのない新しい課題へ取り組み続けていかなければなりません。
そこで重要となるのが「課題解決力」であり、私はこの能力を専門性の高い状況下で鍛えることができるのが大学院の研究における一つのメリットだと思います。具体的には、ゼロからでも知識を収集できる「調べる力」、見えない答えを予測するための「深い思考力」、そして精度の高い議論をするための「伝える力」などが鍛えられたと感じています。
大学院では教えてもらえることは当たり前ではありません、いかに自らが主体的に動けるかによって二年間で得るものには大きな差が生まれると思います。宇都宮大学は成長できる環境が十分整っていると思います。あとは皆さんのやる気次第です。頑張ってください。
仕事で生きている力
私は現在、横浜市役所建築局公共建築部に勤務しています。仕事内容は学校施設の設計工事の契約や工事監督等です。具体的には設計者や施工者、学校との間に立ち、円滑に業務が進められるように調整を行っています。また、教育委員会と学校の基本構想を作っています。
大学時代は、障がい児施設に関する研究をしていました。研究では、施設のスタッフ・保護者へのアンケート調査、施設スタッフへのヒアリング調査、スタッフと子どもの行動観察調査を通して施設の整備指針をまとめました。研究を通して、施設スタッフの方に加えて県庁の職員や教育学部の教授等様々な立場の方と関わる機会があり、多角的な視点を持つことができました。
現在の仕事でも、学校の先生の要望をくみ取り、設計者・施工者に伝える等異なる立場の方と多く関わっています。大学時代に培った多角的で広い視野を持ち取り組む力が今の仕事にも生きていると思います。
土木工学プログラム
- 伊東 可恋
-
2023年度修了生
太平洋セメント株式会社
人と関わることの大切さ
私はコンクリートの性質に興味を持ち、土木材料研究室で大学院修了までの3年間、コンクリートの自己治癒性能に関する研究を行いました。大学院では学生主体となって実験を進めるため、実験テーマと真剣に向き合い、材料に関する知識を深めることができました。また大学院の授業ではグループ作業が多く、学内での発表の他に学外報告会や海外の学会発表に出席する機会があったため、コミュニケーション能力が鍛えられたと思います。
現在は太平洋セメント株式会社の研究所で技術開発に携わっています。毎日が新鮮で、楽しみながら業務に取り組むことができています。材料に関する理解はもちろん必要ですが、チーム員との情報共有やミーティングで発言する上でコミュニケーション能力が必要になる場面が多くあり、大学院での経験が活かされていると感じます。
勉強は大切ですが、それと同じくらい人と関わることも大切だと私は思います。豊富な時間を活用して有意義な学生生活を送ってください。
- 藤岡 光
-
2021年度修了生
宇都宮大学大学院地域創生科学研究科博士後期課程
将来につながるチャンス
私は大学院で博士前期課程を修了後、博士後期課程に進学し、現在は橋梁の耐震に関する研究を行っています。
博士前期課程で得られることは次の2点にあるかと思います。1つめは、研究ができる自由な時間です。研究課題に対してじっくり時間をかけて、近道を行かずに、たくさんの失敗をしながら、研究に没頭できる時間が、博士前期課程では得られるのではないでしょうか?2つめは研究者との交流の機会です。博士前期課程では、学会参加などで多くの研究者と討論や交流をする機会を経験し、たくさんの考え方を知り、自分の考え方が奥深いものになっていきます。
わたしは、これらの経験から、研究する時間が楽しく、これからも研究に関する様々な経験をしたいと考え、博士後期課程に進学しました。博士前期課程では将来につながるチャンスをたくさん与えてくれます。特に、将来の進路に悩んでいる人は、博士前期課程で勉強してみてはいかがでしょうか。
- 高橋 健太郎
-
2020年度修了生
大日本コンサルタント株式会社
考える力
私は大日本コンサルタント株式会社で、橋梁の設計に携わっています。
この業界で活躍するためには、多くの専門的な知識が必要になります。また、設計には様々な基準が設けられており、なぜそのような基準が設けられているのか、しっかり考えなければ、よい構造物を造ることができません。
大学院では、橋梁の免震支承に関する研究を行っていました。振動実験やシミュレーション解析などを行い、橋梁に関する知識を学びながら、深く考えることの大切さを学びました。
さらに、学会発表や論文投稿をすることにより、自分の研究の成果を発信する機会が得られました。私は、自分の意見や成果を整理し、まとめて誰かに伝えるということは少し苦手でしたが、学会発表などを通して、相手にわかりやすく伝える力を鍛えることできました。
地域創生科学研究科の学習の中で、これらの「考える力」を培った経験は、これからも大いに役立つことだと感じています。
農業土木学プログラム
- 石崎 弘真
-
2021年度修了生
株式会社水環境プランニング
出会いときっかけ
私は修了後、株式会社水環境プランニングの計画部に所属しています。業務内容は、現状の水路や側溝、貯水池などをモデルに落とし込みシミュレーションをして、浸水対策の提案を行っています。
この業務には、大学時代に農業土木で学んだ知識や研究でモデルやソフトを扱った経験が活かされています。そして、この会社は経験豊富なドクターの方が勧めてくれた会社です。いつどこに人生を変えるきっかけがあるかはわかりません。出会いは大切であるとつくづく感じます。
そのようなきっかけをくれた宇都宮大学は先生方との距離が近く、アットホームな雰囲気で専門的な知識が学べる環境が整っています。イベントも多く、たくさんの出会いときっかけがあることと思います。迷っていても飛び込んでみれば、その先が広がっていて、充実した大学生活が送れることと思います。大学生活を楽しんでください。
土木のすゝめ
私は修了後、埼玉県の職員として働いています。県の職員と言っても様々な仕事があり、私は県土整備部に所属しています。県土整備部では、道路や河川、橋梁など県土の骨格となる基盤の整備を行なっています。業務に忙殺される毎日ですが、自らの頑張りが土木構造物となって、出来上がったときの達成感は言うまでもありません。大学時代には多くの人と出会い、様々なことを学びましたが、特に研究活動では、論理的な思考力と自分の意見を最大限伝えるコミュニケーション能力を養うことができました。これらの力は、日々の仕事を進める上でも大いに役立っています。宇都宮大学では、自分のやりたいことを実現できる環境が整っていると思います。迷っていても、とりあえず飛び込んでみると意外と吉だったりもします。貴重な環境を存分に楽しみながら、大学生活を満喫してください
グローバル・エリアスタディーズプログラム
“七転び八起き” 確かな歩み
私の修士課程は、多くの素晴らしい出会いに恵まれ、大きく成長できた時間でした。学部で工学を学んでいた私は、定性的な研究手法に馴染めず、悩む時間も多くありましたが、常に私を支えてくれたのは指導教員やゼミの仲間でした。ゼミでは、産官学民の多様なアクターと関わり、物事を多面的に捉え、主体的に行動する力も養われました。さらに、自治体主催のまちづくり提案では2位を受賞し、まちづくりの面白さと、グリーンインフラの重要性を再認識する機会となりました。こうした経験を通じて、現場に近いアクターでは対処できない問題に対し、国の立場からアプローチしたいという思いが強くなりました。現在は国の行政官として、国民の痛みや願いを真摯に汲み取り、日本社会を次の世代により良いものにして渡すことを目指しています。
振り返れば、修士課程は、向かい風の中で目的地を見失い、立ち尽くすような瞬間も多くありましたが、その都度、立ち向かう術を少しずつ身につけてきました。これから先、さらに強い風と遭遇するかもしれませんが、修士課程で得た所作と出会いや経験は、いつも私を支えてくれると信じています。
- 横山 友輝
-
2022年度修了生
日本オラクル株式会社
いかなる環境でも生きる「力」
私は、IT業界で社会人生活を送っています。大学院では、アフリカにおける紛争後平和構築を研究していました。ここでは、大学院での経験が、社会人生活にどのように生かされるのか、「情報を処理する力」に着目して紹介します。
この力は、膨大な情報の前で尻込みせず、優先順位をつけ、資料を粘り強く読み込む力と言い換えることができるでしょう。社会人は、プロジェクト推進において、お客様情報や社内規定など、数多くの情報を処理する必要があります。その際に、大学院で養うことができる情報処理の力が生かされます。
私自身、大学院在籍時は、研究活動の一環で国連大学が主催する大学院生向けのセミナーに参加するなど、多くの情報を得て、それらと向き合う時間に恵まれました。このような経験から、情報処理の力を養うことができたと考えます。
その他にも、宇都宮大学大学院では、海外での調査研究など多くの成長機会があります。ぜひ、大学院進学を進路の選択肢の1つにしてみてはいかがでしょうか。
多文化共生学プログラム
- 胡 一騰
-
2023年度修了生
三光ソフラン株式会社
文系大学院でもメリットだらけ
2019年の夏、中国で日本語を専攻して、大学を卒業しました。異国への期待を抱いて日本へ来ました。そして、2年目に宇都宮大学大学院地域創生科学研究科に入学しました。
自分は社会福祉学を研究するために入学しましたが、実際に入ってみた結果、福祉以外に多文化共生、教育、法律、芸術、文学など様々な分野に触れることができました。
「文系大学院生は就職で不利になる」のような噂を耳にすることは珍しくないと思いますが、実は、大学院での2年間に経験したことは今後、仕事をする上で大切なことでした。
私は大学院卒業後、不動産営業職になりました。大学院で、大量の文献を読み、インタビューをしてその情報をまとめて、他の人に向けてわかりやすく書き換えて提出という膨大なインプットとアウトプットをし、情報の収集、整理力とコミュニケーション力は鍛えられています。この能力は今の営業職で非常に役立ちます。顧客のニーズを理解し、関係を築く能力が営業の成功に直結します。
これからも大学院の経験を大事にして社会的使命感を持って働くと思います。
- 冨金原 拓馬
-
2023年度修了生
私立高校 地歴公民科講師
大学院での学びと社会生活
私は現在、栃木県内の私立高校に講師として勤務しています。大学院では宇都宮の歴史を専門に研究していましたので、日本全国の歴史を通史的に学ぶ高校歴史科でその専門知識が活きる機会はそう多くありません。しかし、研究の中で培った課題解決力は、講師生活で活かされています。
課題解決力は、ゼロから情報を収集する力、見えない答えを予測する思考力、自身の考えを聞き手に伝える力などで構成されています。特に本学では、他専攻の講義受講が必須である点や、他プログラム専攻の学生とグループを作り、地域創生を目指したプロジェクトを開発する点など、文理融合・学際的な課題解決力を育む機会が多く設けられています。
現在は、いかに生徒に歴史へ興味を持ってもらうか、他科目との教科横断的な学びを目指した授業とは何かなど、授業設計において課題解決力が活かされています。
大学院での学びは、社会生活の中で必ず生きてきます。大学院で学んでみたいと思っている皆さんは、ぜひ本研究科で学んでください!
まだ遅くない、今日から始めよう
2009年2月韓国から日本に渡って11年目になる2020年の春、宇都宮大学大学院の地域創生科学研究科でしばらくぶりの学生生活を始めました。日本で家族を作り、家庭を築きながら自分の立場や自分の子どもについて考えて見ることが多くありまして。学校で勉強をする機会が出来た時には今更学生になる事に不安もありましたが、自分のような環境に置かれている人たちについて知りたいとの思いから多文化共生学プログラムを選び田巻先生と出会うことになりました。ゼミでは他の留学生たちや日本人の学生たちと共に学びながら研究のため他県の自主夜間中学までフィールドワークに出たり、「HANDS」活動の一つである宇都宮市「子ども国際理解サマースクール」にも自分の子どもと参加して、宇都宮市の小学生たちが日本以外の国についてどのような考えや興味を持っているのかを覚える機会もありました。宇都宮大学大学院での時間は私にも家族にも多様な経験ができて、色々を考えさせる良い2年間でした。
大学院での学びからより外国にルーツがある子どもや人のための仕事をやりたいと思い自分の新しい勉強にも取り組みながら、ゼミで発足から関わってきた「とちぎ自主夜間中学」と付き合っています。これからも遅いと思わず今自分が出来る事に挑戦しながら現在を楽しみたいと思います。
地域人間発達支援学プログラム
広い視野で物事を捉える力へ
地域創生科学研究科での学びは、地域課題に多角的に向き合う視点や、調査・分析を通じて課題解決の糸口を見出す力を養うことができました。現在は市役所の学校教育課に勤務していますが、直接的に大学院での研究内容を活かす場面はまだ多くありません。しかし、地域に根ざした教育施策を考える際や、今後地域と学校が連携した取組を進めていく上で、大学院で培った経験は大いに役立つと確信しています。特に、那須塩原市の図書館「みるる」や、大田原市の「芸術文化研究所」などの実地へ見学に行ったことが強く記憶に残っています。また、地域住民や関係者との合意形成の難しさや、実践に至るまでのプロセスをプログラムの中で議論したことは、行政の立場として現場に寄り添う姿勢や、広い視野で物事を捉える力として活かされています。今後も、地域創生の視点を持って行政に貢献していきたいと考えています。
- 張 鵬宇
-
2023年度修了生
代々木アニメーション学院
既に身に付けた知識で新しい分野に挑戦する
学部生時代に、中国のマスコミ系大学でネットワーク及びニューメディアを専攻していました。特に動画制作に関しては、その基礎的知識を身に付け、多くの制作も行ってきました。しかし、動画の実用化については、経験少なく、より多くの経験を積むために新しい分野に挑戦することにしました。
新しい分野を考慮した際に、宇都宮大学の「3C精神」を知りました。具体的には「Challenge:主体的に挑戦し、Change:自らを変え、Contribution:広く社会に貢献する」です。この「3C精神」の理念に基づいた新たな学びとして「情報教育・教育工学」を選択し、共同教育学部の研究生を申請しました。研究生の時は、担当の教授は私に「情報教育・教育工学」に関する学部の授業をたくさん参加させてくれ、毎週ゼミを行いました。とても勉強になりました。特に、日本のGIGAスクール構想を知り、これまで身につけた動画制作の知識を活用できるのではないかと考えて研究に取り組みました。地域人間発達支援学プログラムに進学した後も、教育関連の授業に多く参加し、その中で教授たちの熱心な指導によって学校教育の現状や課題など新たなことを多く学ぶことができました。また研究の方法についても指導されることで、自分の研究への挑戦に自信を持つことができました。最終的には、自分が作成した動画教材は子どもたちの学習意欲の向上や構成などの観点で有用性があることがわかり、達成感を得ることができました。修了後も宇都宮大学の「3C精神」とこの2年間の経験を活かしていきたいと思います。
- 山口 智也
-
2022年度修了生
栃木県立高等学校 保健体育教師
対話を通じた学びによる人間的成長
大学院では、人間の生涯の発達について多様な側面から学び、現在はその発達段階の中で未成年から成人への移行期という重要な段階にいる高校生を相手に仕事をしています。毎日の授業準備や生徒指導などは大変ではありますが、充実した日々を過ごしています。
私が大学院の生活を送る上で一番大切にしていたのは、質の高い時間を過ごすことです。将来の自分にとって必要な学びを選択し、それに集中し、毎日続けることで学部時代よりも更に濃密な学びの時間を経験することができました。
2年間の学びの中で、特に現在の仕事に活きていると感じるのが、大学の先生方、現職の中学・高校の先生方との対話を通じた学びです。授業で生じた疑問はもちろん、私が感じていた子どもの発達・学校教育・地域社会に関する疑問点について、多くの先生から、それぞれの立場を踏まえたご意見をいただき、新たな気づきがあったり、自分の考えに自信を持ったりすることができました。
研究はもちろん、自分の価値観を広げる環境が整っている研究科だと思います。大学院進学を考えている皆さん、ぜひ本研究科で学んでください。
光工学プログラム
光とともに未来をデザイン
2025年春、株式会社タムロンに入社し、光学設計者としてのキャリアを歩み始めました。大学で開催された企業説明会や、光工学プログラムならではの光学メーカー社員による設計講義、さらに元光学設計者である社会人ドクターとの交流を通じて、光学設計という職に魅力を感じたことが入社のきっかけでした。
入社後は、お客様が満足する光学製品を開発するために、光学理論や経験、そして瞬間的な閃きから最適解を導き出す職人のような先輩社員の姿に憧れ、日々努力を重ねています。
地域創生科学研究科では空中結像技術の研究に取り組み、光学系の設計や光線追跡シミュレーションを実施しました。また学会発表や展示会に参加した際、企業の方々と積極的に質問や会話を交わしていたので、この経験が入社後の他部署との連携にも活かされています。将来的には国外での仕事にも役立てていきたいです。
研究室での多くの挑戦と失敗、その中で得た学びが私の糧になっています。これらの経験を土台にして、未来の課題に果敢に挑み、新たな価値を創造する光学設計者を目指していきます。
- 吉田 圭佑
-
2021年度修了生
浜松ホトニクス株式会社
研究者として生きる。
私は大学時代の専攻を活かせる研究開発職に就きたく、浜松ホトニクスに入社しました。光技術は私たちの暮らしの様々な場面で応用され、科学の発展に大きく貢献してきたkeyテクノロジーです。光にはまだまだ未知な点が多いですが、次の時代を切り開く大きな可能性を秘めています。そんな光のもつ無限の可能性を、この仕事を通して追究していきたいと思っています。
学生時代はプラズマ工学について学んでおり、特に電磁波とプラズマの相互作用に関してシミュレーション解析を行っていました。電磁波とプラズマの引き起こす物理は複雑かつ難解のため挫けそうになった時もありましたが、落ち着いて丁寧にロジックを再構築したり、一度モデルを簡単化して考察したりなど、様々なアプローチをかけて現象の解明に努めました。
2年間の大学院生活を経て研究の楽しさを知り、それを職にすることができました。光技術を通してより豊かな生活が実現できるよう、今後も精進してまいります。
- 早崎 亮平
-
2020年度修了生
アダマンド並木精密宝石株式会社
専門性を生かした仕事
私は、フォトニクス技術本部の試作開発係に所属しており、光通信部品の設計や試作品や製品の開発を行う部署で勤務しています。この会社は大学院時代の所属研究室の共同研究先として知り、私が学生時代に学んできた内容や、行ってきた研究とも大きく関連しています。これまでに培った光通信に関する知識は、業務や製品の理解に役立っています。コロナ禍という人とのコミュニケーションが減少している中での入社となりましたが、業務内容の理解ができたことで、仕事に早くなじむことができたと思います。
地域創生科学研究科では、他プログラムの学生との合同で行う講義があります。その際、たびたび自身の研究について説明する機会があり、分かりやすく説明する力やコミュニケーション能力がつき、仕事に生かせるのではないかと思います。
まだまだ学ぶべき内容は多々ありますが、大学で学んできたことや経験したことを下地にし、光通信の発展に寄与できるような製品づくりを行えるようになりたいと思います。
分子農学プログラム
- 塩田 歩夢
-
2024年度修了生
国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
自分を見つめ直す時間として
大学院では植物の微量元素についての研究を行っていました。現在は農研機構に入構し、農業機械の研究グループにて研修を行っています。分野は変わりましたが、今まで経験したことない世界で多くの学びがあり、充実した日々を過ごしています。
大学院へ進学した理由は、研究の道に進みたいという漠然とした思いがあったためです。ただ、研究者として何をしたいのか、その考えは曖昧なままでした。そこで、自身の興味や適正を見直すため、専門性を深めるだけでなく、自分の興味に従って普段関わりのない分野にも触れてみました。大学院の講義は学部の頃以上に多様ですし、ときには外部の勉強会にも参加しました。このときに学んだことは現在の研究に活きることも多く、また何よりも、将来の自分の在り方を決めていく上で大切な時間でした。
この大学院での2年間があったからこそ、研究者として農業と関わる道に進むことができたのだと思います。これからは、研究成果の社会実装まで携わり貢献できるように日々精進していきます。
- 市川 晋太郎
-
2022年度修了生
宇都宮大学大学院地域創生科学研究科博士後期課程
将来を見出す時間
現在、私は博士後期課程で植物細胞の観察に関する研究に取り組んでいます。学部生の頃、卒業研究を進めるにつれ、少しずつ出る結果に楽しさを見出すようになりました。研究の楽しさを追い求めるうちに、博士前期課程では研究に没頭する生活が当たり前になっていました。将来の進路について悩んだ時期もありましたが、取り組んでいる研究をさらに深めたいと思い、博士後期課程への進学を決意しました。
博士前期過程では、自分のやりたいことや興味のあることに向き合える時間がたくさんあります。大学院生である以上、研究活動には一定の時間を割く必要がありますが、残りの時間をどのように使うかは自分次第です。私のように研究に取り組むも良し、英語学習などに時間を充てるのも良しです。皆さんは貴重な2年間をどのように過ごしますか?
- 柏瀬 郁菜
-
2020年度修了生
ジョルディカワムラ
大学生活を糧に
私は鉢花の育種、生産および販売の仕事ができる会社に勤めています。現在は、主に花の生産管理の業務を教わっているところです。
大学では植物育種学研究室に所属しており、研究を進める過程で得られた知識や経験は業務内容を理解するためにとても役立っています。ただ、花の生産管理には育種や植物の知識だけでなく、土壌や肥料、病害虫などの知識も必要となってきます。植物の状態は刻々と変化するので、幅広い知識を身に着けられるよう、日々勉強しています。
これから大学や大学院で学ぶみなさんは、専門分野を決めて研究をすることになると思いますが、幅広くいろいろなことに挑戦しておくと思わぬ経験が役に立つこともあります。身構える必要はありませんが、サークルで工程表を作ったことや研究室で試薬の管理をしたことなど、細かいことも経験として身になっています。積極的に様々な経験をして、大学生活を楽しんでください。
物質環境化学プログラム
- 篠原 廉
-
2024年度修了生
デクセリアルズ株式会社
研究活動を通じた挑戦と成長
私は無機材質化学研究室に所属し、鉄複合酸化物光触媒に関する研究に取り組みました。この材料は既に知られているものですが、性能にはさまざまな要因が複雑に絡み合っており、十分に解明されていない点が多くありました。実験を通じてそれらの要因を一つずつ検討し、新たな知見を得る過程は非常に刺激的でした。学会発表や論文執筆の機会もいただき、自分の考えを外部に伝える難しさとやりがいを実感しました。現在は電子部品や接合材料などを手掛けるデクセリアルズ株式会社で、非常に充実した研修を終えて日々業務に励んでいます。大学院で培った、未知の課題に柔軟に取り組む姿勢は、今の仕事にも大いに活かされています。ぜひ積極的に挑戦を楽しんでください。
- 前田 美波
-
2022年度修了生
株式会社プロテリアル
研究室で学んだこと
私は特殊鋼や電線, 磁石などを取り扱う会社に勤務しています。磁性材料の研究開発部に所属し、現在は工場を回って磁石の生産過程を学んでいます。学生時代は計測化学研究室で鉄の腐食の研究を行っていました。その過程として様々な分析機器の利用だけでなく、3Dプリンターの利用や画像解析などの化学分野ではないたくさんのことに挑戦する機会を頂けました。磁性材料について研究するのは初めてですが、新しい知識を楽しみながら学ぶことができているのは、大学院や研究室で培った他分野を前のめりで学ぶ姿勢のおかげだと実感しています。また、研究した内容や結果が仕事に直結するとは限りませんが、そこに至るまでの過程は今後活かせるのではないかと思います。最後になりますが、思うように結果が振るわなかったとしても経験や学んだ知識は自分の糧になると思いますので、楽しみながら色々なことに挑戦してみてください。
- 粟屋 友貴
-
2020年度修了生
YKK AP株式会社 生産技術
伝える技術
私は、建築用の製品を扱う会社に勤務しています。私の主な仕事内容は製品を安全に、安く、効率良く作る方法を提案し、実行することです。この仕事に取り組むに当たり、宇都宮大学で得た知識や課題に対する考え方、コミュニケーション能力は非常に重要だと感じています。特に、自分の考えを人に伝える技術は、専門分野関係なく重要だと感じています。なぜなら、提案した企画を実行するためには、上司を説得して会社から資金を出してもらう必要があるからです。大学院では、学会や学内での発表、他分野の人との講義の中で自分の研究や考えを発表する機会があります。これらの機会をうまく利用して、自分の考えを人に伝える技術を身に付けてみてください。特に他分野の人との交流は、どうすれば伝わるのかを考える良い経験になっています。また、勉強以外にも友人、先輩後輩、先生との関わりも役に立つので、様々なことに挑戦して良い人間関係を作ってください。
農芸化学プログラム
- 斎藤 健
-
2024年度修了生
(株)ワールドインテック
仕事中に感じた宇大院での経験
私は微生物関連の検査をする仕事に就きまだ数ヶ月ですが、院での経験が仕事に活きた場面を2つご紹介します。
1つ目は、学部より知識・技術を付けられ、院からは工農総合となり幅広い知識もカバーでき、仕事に馴染みやすかったです。
私は、研究室でも微生物を扱っていたため、その経験が役立っています。また、講義で学んだ質量分析機器の原理理解は、実際に職場で使用することになった際に大きなアドバンテージとなりました。専門知識だけでなく、機器や試薬の市場価値を理解していたことで、上司や先輩との会話も弾み、職場環境にスムーズに溶け込むことができました。
2つ目は、目上の人との会話に抵抗が少なくなりました。職場では目上の人と会話する機会が多いですが、学部は同年代との作業が多く、経験が乏しかったです。院では、他研究室の先生に実験を教えて頂く事や自転車サークルで活動し、同じ趣味の池田学長とお話する機会を頂くなどの経験を積めました。
就職して気づいたのは、新卒の業務は標準化されたマニュアルに沿って進められることが多いという点です。しかし、研究で培った「自ら考え、解決策を見出す力」が、日々の業務における創意工夫や問題解決に自信を与えてくれています。
- 横山 陽奈
-
2022年度修了生
栄研化学株式会社 那須工場製造部
大学で得た糧
私は臨床検査薬の製造を行う会社に勤めています。現在は、遺伝子関連分野の試薬を製造する現場で業務を教わっています。
製造現場では、様々なバックグラウンドをもつ先輩方とチーム一丸となって作業をする必要があります。そんな中で、進捗状況の伝達やトラブルの際の状況など、情報を適切に伝える力は重要だと感じています。それによって、チーム全体の仕事の効率があがったり、困ったときは周りの人にうまくサポートしてもらえたりできると感じています。
大学院では、研究内容や自分の考えを人に発表する機会が多く、人にわかりやすく伝える力が身についたと思います。また、発表資料の作成などで、視覚的な伝え方についても身につけることができました。大学院での経験があったからこそ、今、そしてこれからの伝える力の糧になっていると感じます。
学生のみなさんには、経験できる発表の機会を将来の自分の糧になるとも捉えて、挑戦してみてほしいです。
- 島影 凌
-
2020年度修了生
株式会社ケミクレア小名浜工場 製造部門
大学で出会った分野で
私は、宇都宮大学で学ぶ中で知った有機合成の世界に惹かれ、その研究活動に取り組んでいました。そして現在、株式会社ケミクレア小名浜工場で、医療品原薬などの有機化合物の製造に携わっています。工場での生産は、研究室で使うフラスコとは比べ物にならない大規模な設備で行います。しかし、その管理・制御は計測機器に頼るだけでなく、研究と同様に自分の目で見て状況を判断し実行する能力も問われます。また、私が作っているのは人が口にして、人体に影響を及ぼすものです。私たちが携わった製品を摂取する患者さんと、自分を含む作業者の安全も守るために、生産上の衛生管理に大きな責任があります。このような能力や責任が求められる仕事ですが、研究活動を通して得た問題解決能力、有機合成に関する知識や技術、そして安全遵守の態度が、今の私を支えてくれています。
機械知能工学プログラム
- 平久井 悠馬
-
2021年度修了生
宇都宮大学大学院地域創生科学研究科博士後期課程
充実した研究活動
博士前期課程の私の研究は流体力学の点渦系と幾何学特有の量である曲率の関係に焦点を当て、曲率の物理的な意味を解明することで複雑な渦の動きの解析に新たな知見を提供するものです。当時はコロナ禍の影響で学会発表の機会が限られましたが、リモート環境の整備など大学や指導教員の献身的なサポートにより充実した研究生活を送ることができました。この時の経験は私の研究活動の基盤を築く上で貴重なものでした。
現在は同大学の博士後期課程に進学し、引き続き点渦系と曲率に関する研究を深めています。加えて、点渦系以外の物理現象にも曲率での解析を応用するために新たな幾何学理論の構築にも挑戦しており、博士前期課程で培った研究経験がその基盤となっています。大学独自の博士後期課程の授業料免除制度のおかげで充実した研究生活を送ることができており、博士前期課程修了後の進学サポートも充実している良い環境だと思います。
- 竹林 拓海
-
2021年度修了生
本田技研工業株式会社
社会貢献を常に考えるエンジニアになるために。
私は大学院2年間で様々な経験を得ることができました。私は自動車の自動運転に関心があり、自動運転に近い機能を持つ自律移動ロボットの研究をしていました。自律移動ロボットは物の配達や高齢者の移動支援、施設内の警備など様々な用途を目的に研究開発が行われます。そして実際にこれらの用途に沿った検証を通し、完成へと追究を重ねます。私が所属していた研究室では、まさにこの方針で研究することができました。開発したロボットを商業施設やロボットの実験特区で実験し、各環境でしか直面することのできないトラブルに見舞われながらも、原因を追求し技術を向上させていきます。そして展示会やロボット展での企業・研究機関等との技術交流を通してアピールしながら、開発しているロボットの必要性を実感することもありました。
現在は実習で完成車組立業務に携わっており、実習後は自動運転の制御システムの開発業務に携わります。大学院で培ってきた経験を活かし、私の夢である「交通事故ゼロの自動車社会の構築」を実現します。
大学での経験を生かして
卒業後は、日立建機に就職し日々頑張っています。仕事内容は、建設機械の設計・開発です。配属されて間もないので、現在はCADや製品の勉強をしています。社会人になり数ヶ月間経ちましたが、仕事をする上で、専門的・技術的な知識以外にも重要なことがあると感じています。1つ目は、自分で考えて行動することです。主体性を持ち、計画的に行動する必要があります。2つ目は、コミュニケーション能力です。分からないことは積極的に質問し、自分の意見をしっかり伝えることが重要です。私は、これら2つのことを実践するにあたり、大学での経験が役立っています。まず、研究活動では、試行錯誤しながら研究を進めるため、自分で考える力を身に付けることができました。さらに、ゼミや学会など人前で発表する機会が多くありました。他プログラムとの交流もあるので、コミュニケーション能力を鍛えることができました。このように大学で身に着けた力を活かして、今後仕事をしていきます。
- 東谷 恒汰
-
2022年度修了生
NTTアノードエナジー株式会社
周りから求められる人材に
私は現在、通信を途絶えさせない安心安全な社会を実現させ、エネルギー事業者として脱炭素社会を目指すために、日々精進しております。
大学院ではパワーエレクトロニクスという分野に従事しておりました。社会人として数ヶ月経ちましたが、仕事する上で研究が直接業務に関わることは多くはありません。しかし、研究生活で得た目標に向けて一つ一つ問題を解決していく能力や、日々の進捗報告や学会発表で培う物事を人に伝える力が、大きなアドバンテージとなることを身に染みて痛感しております。
社会では必ず納期という期限が設けられます。そこに向け自分自身でプロセスを考え、計画的に物事を円滑に進めていく能力は大きな力であり、周りからも求められる力となります。 周りから求められる人材に成長するためにも、大学院に進学したことは私にとって正しい選択であったと断言できます。是非、大学院で他の人にはない自分だけの力を磨いてください。
- 髙山 翼
-
2021年度修了生
JA栃木中央会 電算職
農業×IT 異分野融合
私はJA栃木中央会の電算職に就職し、日々精進しております。業務を行う上で、システム関連の知識だけでなく農業の知識も必要となるため、しっかりと勉学に勤しんでおります。大学院では、情報系のプログラムに所属していながらも農業×ITという異分野融合の研究を行っていました。学会発表を通して、わかりやすく説明する力や質問への対応力は身についたと考えています。また、授業においても他プログラムの分野が異なる学生と共にグループワークを行い、様々な考え方や価値観に触れる絶好の機会でした。自分自身の価値観を一方的に押し付けてしまうのではなく、議論を通してどのように落とし込んでいくのかという点は非常に勉強になりました。研究や授業を通して異分野同士の議論を行うことができ、良い経験ができたと感じています。
大学院で培った知識や経験はかけがえのない財産になります。何事にも一生懸命取り組み、失敗を恐れずチャレンジしてほしいと思います。
- 吉澤 裕貴
-
2020年度修了生
本田技研工業株式会社
お客様に喜びを届ける
私は、大学院で学んだ知識や経験を活かし、電動化の技術によってお客様により喜びを感じてもらえるような自動車の開発という夢の実現に向けて進んでいます。大学院では研究だけでなく、授業を通じて様々なプログラムの学生同士でのグループワークを行い、専門の異なる人に自分の考えを正確に伝えるコミュニケーション能力が養うことができました。授業の中には、SDGsを取り上げたものがあり、授業を通じて様々な分野のことについて知る機会を得ることができました。そして、研究や授業を通じて視野を広くすることができ、多角的な物事の捉え方や考え方を養うことができました。また、大学院で養った多角的な物事の捉え方や考え方は多様化する価値観に対して、お客様に喜んでもらえるような製品の開発において、とても重要な能力だと感じています。大学院での研究や授業を通じて学んだことが、昨今の100年に1度の変革期と言われる自動車業界の仕事において糧になると思っています。
農業生産環境保全学プログラム
自分を変えたい方は大学院へ
大学院で得た経験は、今の仕事と私の人生に大いに役立っています。私は大学院時代、ビールに香りや苦みを与えるホップという植物の加工方法について研究していました。そして今は食品メーカーのカゴメで働いています。「食」という部分で研究内容と仕事が共通していることも、大学院時代の学びが今に活きている一因です。しかし、大学院時代の様々な経験には勝りません。大学院に進学するまでの私は消極的でしたが、学会や地域コンクール、大学院進学ガイダンスでの発表、外部との共同研究など、多くの経験をしたことで挑戦へのハードルが低くなりました。今野菜ジュースの製造に携わり、成分が規格内に収まるように調合する仕事をしています。配属されてから日が浅いですが、製造現場で感じた違和感や改善点など自分の意見を発信できているのは大学院に進学したからこそです。今後は1年少し製造現場での業務を経験した後、国内外での調達など、生産全体に携わる仕事に挑戦します。「自分を変えたい」と思っている方に、大学院進学を強く勧めます。
- 島田 光一
-
2021年度修了生
プリマハム株式会社
多分野への関心
私は本大学院において畜産分野の研究を行い、食肉加工メーカーへ就職、現在は研究員として日々業務に勤しんでいます。入社して数か月が経ち、私が実感したことは、「分野を問わず幅広い知識が必要」ということです。食肉加工メーカーといっても、食肉に関する研究だけでなく、多岐に渡る分野への挑戦が必要です。
本大学院では講義を通して多種多様な分野の研究に触れ、時には意見交換ができる機会が多数用意されています。自身の研究に没頭することもできますが、様々な知識を増やすことで物事を多面的に考える力が身に付きます。私自身入社わずかですが、大学院での学びが活きていると実感しています。
自身の専門外のことには興味が湧きづらく、めんどくさいと思うかもしれませんが、ぜひ交流の場で質問を投げ、いろいろな話を聞き、意見交換を多くしてほしいと思います。ひょんなところからその知識が役に立つときがくるかもしれません。
自分の『土台』を広げた大学院
食べることが好き、ゆえに食料供給の現場に興味を持ち、農学の道に進みました。現在、私は農薬メーカーに就職し、技術担当として農薬の試験・調査を行っています。自社剤の特長を見出し、普及販売を技術的側面からサポートするためには、農薬の知識だけでなく農業の現場の知識も必要となります。さらに、公的機関とも情報を共有するため、データを収集・整理し、わかりやすくまとめる力も求められます。
本大学院では他分野・多文化の先生方からご指導を受け、新しい知識や様々な経験に触れることができます。また、物事を多面的にみる力、創造的思考、主体性など自分の『土台』となる力を身に着けることができます。そのため、大学院で得た知識や経験は、仕事でも大いに役立っており、私の財産となっています。
最後に、「心持ちで何事も面白くなる」と皆さんに言いたいです。ぜひ、積極的に物事に取組み、多くのことを吸収してほしいと思います。
森林生産保全学プログラム
- 深谷 航
-
2024年度修了生
東北大学生命科学研究科
自分の「好き」を探求する
現在,私は東北大学生命科学研究科の博士後期課程に進学し,植物の系統進化や分類に関する研究に取り組んでいます.博士後期課程のテーマは学部〜博士前期過程の内容を発展させるものなので,宇都宮大学時代に培った経験が今の研究活動の基盤となっています.私は卒論・修論ともに自身の好きな研究テーマを設定させていただいたおかげで,現在も楽しく,主体的に研究を続けられています.
大学院に進学する動機は,研究,就職,学生生活の延長など様々だと思います.博士前期課程では,多様な講義を受けることで学部時代の学習を補完・発展させることも,講義を最小限に抑えて研究や就活に打ち込むことも,自身で選択できます.博士前期課程は2年間と短いですが,目的を持って主体的に行動することで有意義な時間を過ごせると思います.
- 菊地 真以
-
2023年度修了生
林野庁中部森林管理局
大学で得たもの
私は中部森林管理局の資源活用課に所属し、国有林材の生産と販売に携わっています。学生時代は、森林計画学研究室で森林評価や計画、調査について学んできました。森林計画は林業経営の基本となる分野であり、現在の業務とも関わりが深いです。研究やゼミで得たLiDARやGISに関する知識や技術を活かせる場面も多いです。
大学で得たものは数多くありますが、地域創生科学研究科の特徴的な部分について挙げると、多様な講義を受講したり、他プログラムの学生と交流したりする機会が多いため、幅広い知識のほか、他分野の人にわかりやすく伝えるコミュニケーション能力や様々な視点から考える能力が得られました。業務では所属する課の方以外に、他分野を扱う課の方や国民の皆さまと関わる機会もあり、それらの能力を活かせていると感じています。
今後も大学の講義や研究で得た経験を糧に、業務に取り組んでいきたいと思います。
- 松岡 佑典
-
2020年度修了生
栃木県森林組合連合会
木とともに働く
私は栃木県森林組合連合会の木材流通課に所属し、木材の共販に携わる仕事をしています。学生時代は日本の森林・林業の現状や課題、効率的な林業とは何かについて学びました。実際に木材を扱う業務に携わると、学生の時には知らなかったことも多く、毎日が覚えることで溢れています。
また、日々の業務を進める上で宇都宮大学での研究や論文執筆、学会などを通して得た問題解決のための考え方は非常に役に立っています。
宇都宮大学で林業を学び、今後の林業に対してしっかりとビジョンを持った人達と共に日本の林業を盛り上げていけることを期待しております。